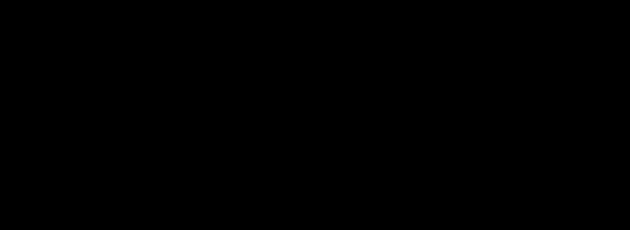ね、うんとうごいてッ
「うッ、むうううわああ、いい、いいわいいわ、あのブス女が恭介に夢中になるのも、あんッあんッ、分かる気がする」
そこは叔母が予約しておいた、わりに有名なシティホテルの一室。
叔母の夫は大学院の教授で、学会関係の仕事でヨーロッパ滞在中だった。
幸か不幸か、私の妻も何日か前から、妊娠後期に入って帰省中だった。
つまり、私と叔母を引き寄せる磁場があのとき、偶然ないくつも折り重なって生じたのである。
自分が大インテリで、テレビ制作会社の幹部でありながら、
「教師、とくに大学教授なんて、本当に世間知らずのバカが多いの。もっとも、テレビ界もバカばっかりだけどさ」
叔母は自嘲ぎみにいい、続けて、
「ごく一部の志を持ってる者を除いて、高給取りのテレビ屋の連中のほとんどはただ視聴率という正体不明の“化け物”、ううん“神話”にすがってる。あはは、庶民の暮らしやニッポンの行く末なんかについて脳みそ使う者なんてごく少数。大事なのは自分の高給と身分安泰だけ。こんなバカ連中にニッポンの将来なんかとても託すことなんてできっこないわ」
女優にしたらトップレベルでいられるくらい美貌と知性を誇る叔母は、ふだんのストレスを発散するみたいにおれに対してかなりストレートな口をきいた。
そんな話も面白くはあったが、おれはおそらく父ひとりしか男は知らないであろう彼女の姉である母と違い(叔母は母の兄弟姉妹の中で末っ子だった)、叔母の奔放ぶりに興味が移っていた。
そこはちょっと庶民は寄りつけないような小料理屋で、ママと叔母は大学時代の同期で友人同士とのことだった。
「さて、と。恭介、今夜はどうする?」
酔ったふりして叔母がいった。叔母が酔ってなどいないのは、そのしっかりとした口調と目の強い光で明らかだった。
「融通無碍、というかテキトー。ふふ、叔母さん次第でどうとでも」
「いうじゃない。でも、やっぱり、オバさんは聞きにくい、なんとかならない」
「じゃ、試験的に今晩だけ怜子さん」
「いいわ、いいじゃん、そのセリフって気にいった、もっとつき合える?」
「ええ、あ、はい、喜んで」
「決まり。まだ夜の八時……40分かあ。ね、バカさんというかパパさんがいないから、いっそ、うちに来ない?」
「え、いや……やっぱり、叔母……あ、いや、怜子サマのプライベートな世界への関わりは遠慮しておきます」
「いいわね、恭介。ますます私は気にいってしまったわ、覚悟しなさい」
「は、あ……?」、
とまじまじと叔母をその日初めて正面から見つめると、叔母はちっとも目をそらさずおれをむさぼるような目つきで見返してきた。そのとき、おれは子供の頃からずっとタブーとして心の内に強固に抑えつけてきたひそかなおもいが崩れ、いや解放されていくのを意識した……。
「ね、恭介、お願いだから……」、
「なに、なんなの……」
「お願い、意地悪しないで。私、あなたと楽しみたいの。昨夜のあのオッサンは仕事がらみのスポンサー。でも、ね、ね、いまは違うわ……あッあッ、いい、いいのいいの、ね、楽しみたい、楽しませて、今夜は二人で心ゆくまで楽しみましょ」
「うん、うんうん、叔母……いや、怜子さん、よおく分かりました」
「じゃ、ね、後ろからもしてくれる」
「喜んで。後ろからでも前からでも……
ううん、タテでもヨコでもナナメでも、怜子さん……怜子が喜ぶことだったら、今夜はなんでもしてあげる」
「だったら……ふわ、ふわっあ、ああ、ああ、うごいて、うんとうごいてえ」
「こ、こう……」
「それよ、それなの、もっとして」
「こうだね、これ……が、好きなんだね……うんッ、ふんッ、はあ、それそれ」
「よいわ、よいわ、はあーん、はッ、ははッ、うっ、うごいて、うごいてえッ」
「こう……うっ、ぐう……こうかい?」
「うわッ、はあッ、それよ、それなの、いい。いい、いいッ、いいいーッ」
叔母の長い両脚がおれの胴を痛いほど締めつけ、上体を快感のあまり反っくり返す。シーツがびしょびしょになるくらいの濡れっぷりだったが、子供の頃からあこがれていた美女を偶然によるものとはいえ、こんなにあっけなく抱けるなど人生は不可解だとおれは改めて思った。